HUB-SBA MAGAZINE
2024年度 経営分析プログラム導入ワークショップの報告会が行われました
2024年08月28日
去る7月12日に本学のインテリジェントホールにて、経営分析プログラムの修士1年生による、導入ワークショップ報告会が行われました。この導入ワークショップは1年生向けに開講されている必修の演習科目で、3クラスに分けて一橋ビジネススクールが重んじる少人数教育を行なっています。当日は、各クラスの代表チームから、研究計画や先行研究の説明、今後の進め方についての報告があり、コメンテーターとして修士2年生の2名が参加し、先輩が後輩をサポートして意見を交わす、経営分析プログラムならではの報告会となりました。
導入ワークショップAクラス代表
研究課題:「企業の消費者へのESG情報開示が消費者の購買行動に与える影響」

企業のESGに対する取り組み(以下ESG活動)の情報提供の度合いは、消費者の購買行動に影響を与えているのかについて、「企業のESG活動の情報は消費者の購買行動を促進する」、「コモディティ化している業種ならば企業のESG活動の情報が消費者の購買行動に与える影響がより大きい」という2つの仮説を立てて検証します。これまではESGに配慮した取り組みは元来、企業が社会的責任を果たしていることを、投資家にアピールする目的で行われていた側面が強かったですが、近年はESG活動の普及により認知度の高まりが見られ、消費者のエシカルな購買行動における判断材料として用いられることも増えているということがあげられます。特にコモディティ化している財・サービスでは機能的な差別化が難しいため、ESG活動の情報が情緒的な差別化になっている可能性があります。先行研究では消費者へのアンケート調査が用いられていますが、正確な回答を聞き出すことはできないという問題点があると考えています。したがって、本研究では、ESGに関連する単語をリストアップし、このESG単語が、各企業のウェブサイトにおいてどの程度使用されているかをテキストマイニングすることによって計測し、ESGスコアを作成する。その後、パネル回帰分析を用いて、ESG情報の提供が、実際に消費者の購買行動に正の影響を及ぼすのを分析します。
導入ワークショップBクラス代表
研究課題:「ガバナンス構造が企業の投資行動に与える影響―取締役のスキル・ダイバーシティに基づく分析―」

本研究の背景には、日本企業のグローバル競争力の低下があるなかで、近年、日本で進展しているガバナンス改革がどのような影響を与えているのかという問題意識があります。企業価値を高めるためには成長投資が不可欠なのに対して、近年、設備投資・研究開発投資はほとんど横ばいで推移しています。一方で、預貯金についてはリーマンショック以降、右肩上がりとなっています。日本企業の投資活動の決定要因や投資活動の消極性の背後にはどういった要因があるのかを疑問とし、関連する議論として「Quiet Life仮説」※1を前提に、「取締役のスキル・ダイバーシティの差は、投資行動の消極性に影響するか」を主題として研究を進めていきます。仮説としては、①規律的スキル(財務、法務、リスクマネジメント)の割合が高い企業は、投資が消極的になる。②ボード・ダイバーシティによって、事業機会やリスクに対する認知能力が向上し、創造性が高まることで、投資の消極性が緩和されると考えます。本研究では、取締役のスキル・マトリックス情報を基に多様性評価を行うため、東京証券取引所に上場し、スキル・マトリックスを開示している企業を対象とし、分析を進めています。
※1 Quiet Life仮説:株主からの規律が弱いと、経営者が保身のためにM&AやR&Dを含むリスクの高い投資や組織再編などの難しい判断を行うことを回避するという仮説。
導入ワークショップCクラス代表
研究課題:「取締役会におけるジェンダー平等はROA及びトービンのQの向上につながるか」
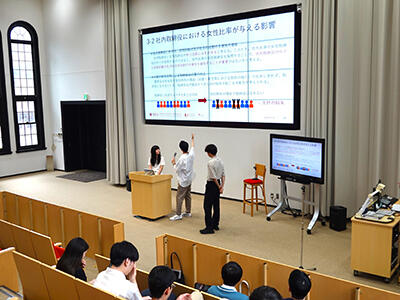
今回の研究課題として、SDGsの目標5「ジェンダー平等」に着目しています。ジェンダー平等のターゲット5.5では、「政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参画及び平等なリーダーシップの機会を確保する」と定義づけられていますが、これが倫理的な観点のみならず、企業業績においても好影響があるのか疑問に感じたため、今回のテーマに設定しました。問題意識として、日本の女性取締役比率は増加傾向にありますが、海外と比較すると低い水準にあります。また、これらのことに着目し、主題を「取締役会におけるジェンダー平等は企業業績の向上に繋がるか」として、調査においては取締役全体に占める女性比率だけでなく、社内取締役に占める女性比率にも注目していきます。その上で、取締役に占める女性比率がROA(総資産利益率)及びトービンのQ※2を向上させるか、ということを検証します。今後の研究の発展性としては、同じ業界の同規模の企業の比較で、業績が高い企業と低い企業の差について、女性比率をしっかり向上させながら企業価値に繋げているか、そうでないのかを分析することもできると考えています。
※2 トービンのq:株式市場で評価された企業の価値(株式時価総額と負債総額の合計)を資本の再取得価格(現存する資本を全て買い換えるために必要となる費用総額)で割ったもの。
担当教員コメント
加賀谷哲之 先生
導入ワークショップでは、社会科学的思考を習得することや論理的に表現するということを学ぶ、という狙いに基づき、各クラスが運営されてまいりました。受講生の皆様の熱心な取り組みにより、企業経営を分析対象として、社会科学的にロジックを積み上げ、その分析・検証手法を選択し、結果を論理的に表現するという導入ワークショップの目的を十二分に達成できたと感じています。ただし、今回、設計いただいた研究計画から、実際にさまざまな示唆や知見を導き出すうえでは不十分であり、研究のほんの出発点にたどりついたにすぎないということを同時に実感されていると思います。修士2年生からのコメントややり取りを通じて、さらに分析手法を学び、ロジックを学ぶことの重要性も同時に体感いただけたと思います。夏休みを効果的に活用し、有意義な時間を過ごしていただきたいと思います。
高田直樹 先生
春夏学期の基礎的なトレーニングの成果が着実に現れていると感じました。その一方で、皆さんが経営分析プログラムに所属していることを踏まえると、実践的な文脈とのつながりを一層意識し、深めていくことが重要ではないかとも感じました。研究においては、特定のテーマを徹底的に掘り下げることが求められるため、実践の文脈から離れすぎて、理論と実践のバランスを欠いてしまう恐れがあります。今後は、さらに幅広い知識に触れ、視野を広げながら、実践に結びついた研究を意識していただきたいと思います。秋冬学期の基礎ワークショップで各クラスの報告を聴く機会を、今から楽しみにしております。
熊本方雄 先生
各クラスの代表チームの報告は、実務的にも学術的にも大変意義深いものであったと高く評価しております。また本日報告されなかった各クラスのチームの研究も非常に興味深いものであったと思います。今回、修士2年のコメンテーターの方々からは、大変鋭い質問をしていただきました。経営分析プログラムの特徴というのは、グループワークを通じて、横のつながりがあるというのが大きな特徴だと思っています。また、修士2年の先輩方が来てくださって、後輩にコメントをするといった縦のつながりというのも、この経営分析プログラムの一つの財産だと思っています。コメンテーターのお二人も昨年の発表の際には、先輩からの鋭いコメントをきちんと受け止めて、今度は次の代に引き継いでくださったということで、心強く、頼もしく思っております。
★先輩からのアドバイス★
コメンテーターとして、修士2年の先輩2名が参加し、鋭い視点からの質問や昨年の自分たちの研究発表の経験からのアドバイスがありました。例えば、「主題と方法論が一致しているのか」や「調査対象企業の選定方法は適切なのか」、「その仮説は本当にそうなのか」ということについて、第三者の目線で問い、研究内容がよりブラッシュアップするためのヒントや気づきを与えるための質問を投げかける場面もありました。